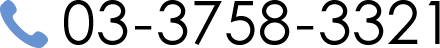黄綬褒章(現代の名工) 東城 佶 *2017年勇退
 [プロフィール]
[プロフィール]
昭和7年生まれ。
千葉県出身。
秋本ダイカストを経て、昭和23年3月電化鍍金工業所(電化皮膜工業前身)入社。
陽極酸化処理(アルマイト)全般を担当。
職務に誠実に働いてきた60年。
技術に携わる人間の最高の栄誉「黄綬褒章」を拝受。
2017年6月 引退。
社長が太っ腹だったのですよ
「黄綬褒章を拝受いたしました」。
そう聞くと、自分と自分の技術を自慢する職人を思い浮かべるかもしれない。
だが、黄綬褒章という栄誉を受けた感想を聞かれても、
「本来なら社員ではなく、経営者が拝受するものなのですよ。私を推薦してくれて、社長は随分太っ腹な人だと思いました。」
と答える東城は、決して人前に出ようとしない、控えめで物静かな、そして優しい職人である。
電化皮膜工業は、日本で最初に硬質アルマイトの工業化に成功した会社である。
第二次戦後、アルミニウムが不足していたため飛行機の残骸を拾ってきて、硬質アルマイトを付け始めた。
あとになって解ったことが、飛行機はジュラルミン(A20系)でできているので、1番アルマイトをつけにくい材料だということ。
そのため、電化皮膜工業では非常に苦労して技術を磨いていた。
その頃、日本ではアルマイトのJIS規格は存在していたが、硬質アルマイトの統一規格はなかった。当時は、普通のアルマイトを厚くつけて、硬質アルマイトと呼んでいる会社もあった。
そのため日本で統一した規格を作る必要があり、通商産業省から要請をうけ、電化皮膜工業は硬質アルマイトのJIS規格の策定に協力した。
このとき、東城は耐磨耗、耐食性、材料の種類などの実験を行い、基礎データを作る仕事に携わった。硬質アルマイトの標準化に尽力したのである。
このときの功績が、黄綬褒章の授章までつながった。
硬質アルマイト処理業界では、現代の名工になったのも、黄綬褒章を授章したのも、東城が日本で最初の人物である。
世界にひとつしかない指輪
 最初に就職したのは「秋本ダイカスト」という、先代の社長の弟が経営していた会社。
最初に就職したのは「秋本ダイカスト」という、先代の社長の弟が経営していた会社。
就職した当時は、まだ日本が第二次世界大戦の痛手から完全に立ち直っていない頃。
どんな仕事でも、仕事ができればよいと思っていた時代だった。
「最初はダイカストをやっていましてね、モーターを作っていました。藤沢にある会社から大船へリヤカーで品物を持ってきて加工する。加工が終わるとまたリヤカーで運ぶのです。モーターのブラシのところのダイカスト製品ですよね。その頃は、機械加工ではなく、手動でやっていました。」
その会社から電化鍍金工業所(現在の電化皮膜工業)に入社することになった。
その当時はめっき処理の会社だったが、昭和25年頃にアルマイト主体の会社に変わった。
趣味的な面白さがあって、めっきからアルマイト処理に仕事の内容が変わっても、東城にはあまり抵抗がなかった。
「仕事の暇をみては、自分でアルミ線をバフかけてきれいに磨いて、かまぼこ型にしましてね。それで、金の色をつけて指輪にして女房にやったことがあるんですよ。世界中探しても、ひとつしかない指輪でした。今頃、女房はあの世でくしゃみをしているかもしれませんね。」
と、ちょっと恥ずかしそうに、社員はあまり知らない当時のことを話してくれた。
「指輪に使う99.9%(スリーナイン)という材料は手に入らなかったけれど、社内で使っている材質に加工して作りました。指輪にしては随分軽いねと、女房に言われましたけれど。」
遊び心をもって何かを作る。
それが現場の仕事にも応用できる。
遊びの中に技術を取り入れる。
それが東城のやり方だ。
東城は細かい手仕事が好きで、物づくりが得意だ。
電化皮膜工業の設備や機械のちょっとした不備は、東城が修理する。
「昔は、ラジオを作ったこともあるのですよ。真空管を4本くらい付けて、秋葉原でトランスとか抵抗とか、コンデンサーなどの部品を買ってきて、それを全部ハンダ付けしてね、スピーカーを付けましてね。自分の作ったものがちゃんと電波を受けて、声がちゃんと聞こえてきたときはうれしかったですね。」
人より考えて仕事をしていたかもしれない
 1級技能士の資格を取得したのは、37歳の頃。
1級技能士の資格を取得したのは、37歳の頃。
昭和の高度経済成長の時代だった。
仕事は次から次へ入ってきて、朝早くから夜遅くまで働かざるを得ない状況だった。
その忙しさの中で、講習に通い、夜に自宅で試験勉強をしていた。
仕事が終わってから、自宅で技術雑誌や本で調べものをしたり、実技のテストのために、道具を持ち帰ってセッティングなどを研究した。
「セッティングをするときは非常に難しくてね。接点のところに跡が残ってはいけないとかね。ものによっては影になると、中に液体が回っていかなくて、電解したときにうまくつかないんですよ。」
当時の思い出に残る出来事がある。試験勉強のためにセッティングの練習をしていたら、同じ講習を受けている仲間から「あれ?、これは先生がおかけになったものですか?」と言われたことがある。
控えめに笑うその姿に、職人ならではの意地と気骨がにじむ。
「その当時から、やっぱり同じ職人の人たちよりは、よく考えて仕事に取り組んでいたように思うのですよ。」
と東城は言う。
そういった資格をとることで、収入にもつながる。
これも勉強のモチベーションアップにつながった。
期待の色にやっとできて、うれしかった
昭和45年の大阪万博のときには、日本政府3号館の入り口に飾るゆりの花の噴水に暖かみのあるアルマイト処理をする仕事をした。
通常、めっき処理後に研磨するとぴかぴかと光る。
つや消しにすると、にぶく寝ぼけたような色になってしまう。
どちらもお客様の要求を満たさない。その中間でしかも乳白色のようなつやのあるものがほしいというのが、お客様のリクエストだ。
東城たちがいろいろ試しても、思うような色にならない。
お客様に何度か色合いを見てもらったら、「もうちょっと、つやが消えたほうがいい」とか、「もうちょっと光った方がいい」とか言われた。
試行錯誤し、やっと「この色でいいですよ。」と言われたときは、「これでよかったんだ」とほっとした。
この飾りは電化皮膜工業で譲り受け、事務所に記念として残してある。
その後、沖縄海洋博では、海面に耐える処理を要求され展示。
その他、銀座通りの1丁目から8町目の表示板や、人工衛星ひまわりへの搭載、東京オリンピックの通信機器材への表面処理など思い出される。
失敗すること。それは一歩前進していく足がかりになる
 電化皮膜工業で、東城の存在は大きい。
電化皮膜工業で、東城の存在は大きい。
東城がそばにいて仕事をしている。
それだけで、若い職人たちには刺激になる。
70歳を過ぎている東城が1日も休まずに出社して、立ち仕事を続ける。
仕事に対する真摯な態度を見て、技術をどうこうという以前に、社員たちは仕事に取り組む姿勢を学んでいる。
東城は、決して自分から「こうしたらよい」とは言わない。
人に教えないわけではない。
悩んでいることに対してはきちんと答えるが、それ以外は自分で考えてもらう。
後輩が失敗しそうになっても、あえて失敗させて考えさせる。
そして、どうしたらよいか質問してきたときに、その答えを教えてあげる。
そういうスタイルで後輩に接している。
失敗しないで、何でもうまくいって、鼻高々になっている。
そんな人間になっては困ると思っているからだ。
「失敗して、苦労して経験したときに、初めてうまくできるんだということを身につけてもらう。それが一番いいですね。」
そして、失敗したときにちゃんとフォローする。
電化皮膜工業には、人が育つしくみがある。
「根性」「我慢」「忍耐」、それは技術を磨くために必要なこと
 与えられた仕事をやり抜こうとする根性。
与えられた仕事をやり抜こうとする根性。
技術を身につけるまでの忍耐・我慢。東城は、そういう心構えがないと技術は身につかないと思っている。
1年足らずでやめてしまっては、何も得るものがないし、次に続かないからだ。
「ただ仕事をするだけではだめです。ただ1日仕事をしたら、給料がもらえるという気持ちでいては、技術は身についていかないのではないでしょうかね。1日1日、1年1年進歩していく気持ちがないと、だめなのではないでしょうかね。」
遊び心を持ちながら、1日1日を大切に勉強と研究を重ね、現代の名工となり、黄綬褒章を拝受した東城の言葉は、控えめながら心に重く響く。
「目標は100歳まで生きること」
 昭和7年生まれの東城は、現在76歳。
昭和7年生まれの東城は、現在76歳。
仕事から引退する世代になっても、東城が働き続ける理由は何か。
ひとつには電化皮膜工業には、定年がないからである。
身につけた技術は一生のもの。いつ退職するかは自分で決めろ。
それが電化皮膜工業の考え方だ。
そして、もうひとつ東城の場合は「100歳まで生きる。」これが目標だからでもある。
電化皮膜工業の社員はそれを本気で応援している。
100歳まで生きるには、健康の維持が大切。
毎日決まった時間に出社して、決まった仕事をして、決まった時間に帰る。
こういう規則正しい生活ができるということは、健康によいと思っている。
自炊をしているので、食べるものにも気を配っている。
もちろん、老後に働くことによって、経済的にもプラスになる。
現在、電化皮膜工業で、ビッグスクーター(バイク)に乗っているのは、20代の社員と70代の東城だけだ。
雨の日以外は、バイクで通勤している。
「よく危ないからやめろとか言われるですけどね、やめてしまうと、がたっと体力が落ちてしまうのが怖いんですよ。バイクに乗っていることで、注意力が働きます。だから、通勤やちょっと出かけるときにバイクに乗っています。十分気をつけて乗っていると、楽しいものですよ。」
東城は現在、週末は山の中の別荘で、カラオケに通っている。
仕事も趣味も含め、生きることそのものを楽しんでいるのだ。